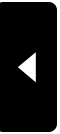2010年02月11日
紀伊国屋での出来事

丸林正則著 「四季の花 クローズアップ」日本カメラ刊です。
ISBN 978-4-8179-0018-0 定価1600円+税
平成22年3月5日発行(あれっ、発行日より早く売られてる……)
身の回りの花を接写(クローズアップ)することで、花の美しさを再発見しよう
という趣旨の本です。
カメラ関係の雑誌でちらっと見て記憶に残っていたものですから買い求めました。
この本の名称は、サブタイトルから全て記録すると
「身近に見られる草花の魅力を引き出す 撮影100花事典 四季の花 クローズアップ」
といいます。
これを、鹿児島市アミュの紀伊国屋の店員に探してもらいました。
店員とのやりとりの中で伝えた情報が
「『身近な花の魅力 100』とうようなタイトルです。写真の本です。
新刊案内のような記事で見ました。この数ヶ月の間に出版されたと思います。事典ではありません」
検索をかけたり、店内を走り回ったりして、ようやく探してくれた本がこれでした。
表紙に見覚えがありましたので、これでありがとうということになったのですが、
タイトルは違うし、事典ということになっているし、
紀伊国屋ではガーデニングのコーナーに並んでいるし……
よく探してくれたなあと思います。
思わず、うちで働きませんかと、名刺を出しそうになりました……(^.^)
2010年02月10日
2010年02月08日
海角7号

ミッテ10に行って「海角7号」を見てきました。
台湾では歴代ナンバーワンのヒットを記録したラブストーリーです。
60年の時間を超えたラブストーリーがベースになって、
音楽という一つの目標に向かうメンバーとそれぞれの出会いを
描いています。
中孝介が、敗戦後恋人を台湾に置いて帰国する男性と、
音楽イベントに日本から出演する本人役の一人二役を演じています。
2月6日には、本人がやってきて舞台挨拶があったようですが
そのときに見に来れなくて残念でした。

2010年02月07日
3D(スリーディー)ドラゴン
久しぶりに、長島珈琲焙煎店(←クリッックして行けます)におじゃましました。
映画「アバター」が大人気で満員だという話題になりましたが、
おもしろいペーパークラフトが飾ってあって、
3Dつながりで盛り上がりました。
→ 3Dドラゴンの型紙はこちら
それで、帰ってきてさっそくSEIKOさんが作っています。

完成した、3Dドラゴンはこちら。

これがどう3Dなのかというのは、作ってからのお楽しみ……(^.^)
上の型紙をクリックして印刷してくださいね。
ちなみに、山折りは Mountain fold 谷折りは Valley fold 。
折り紙は、輸出された日本文化なのですね。
映画「アバター」が大人気で満員だという話題になりましたが、
おもしろいペーパークラフトが飾ってあって、
3Dつながりで盛り上がりました。
→ 3Dドラゴンの型紙はこちら
それで、帰ってきてさっそくSEIKOさんが作っています。

完成した、3Dドラゴンはこちら。

これがどう3Dなのかというのは、作ってからのお楽しみ……(^.^)
上の型紙をクリックして印刷してくださいね。
ちなみに、山折りは Mountain fold 谷折りは Valley fold 。
折り紙は、輸出された日本文化なのですね。
タグ :3Dドラゴン
2010年02月06日
エゴノキ

カキノキ目 エゴノキ科 エゴノキ属 エゴノキ です。
市(いち)集落から嘉徳(かとく)集落に抜ける林道を走っていると、
雨に濡れた路面が白く変わっていたので何だろうと車を停めてみると
雨に打たれて落ちたエゴノキの花でした。
名前の由来は、果実を口に入れると喉や舌を刺激してえぐい(えごい)ことに由来するそうです。

タグ :エゴノキ
2010年02月05日
石だきガジュマル

国道58号線をマングローブパークの先から左折、県道609号線に入ります。
原野農芸博物館を過ぎてまもなくの所に枝を広げています。
名瀬市街から車で約40分。
石だきガジュマルといえばかわいい感じもありますが、
わたしが地元の人から聞いた呼び名は「絞め殺しのガジュマル」でした。
やがて根が包み込んでいる岩はぼろぼろに崩れてしまう運命だそうです。
……(*^.^*)コワッ
2010年02月04日
2010年02月03日
湯湾岳

與湾大親の石碑の右側の細い道を入っていくと
5分ほどで、奄美大島の最高地点の標識が立っています。

標識を真上から見たところです。
「奄美岳 日本固有地 694」と書いてあります。
與湾大親の石碑の後ろに建っていた御堂にも「奄美岳大師御堂」と書いてありました。
奄美民話の会の嘉原カオリさんがホライゾン19号にアマミコ神話について書いていらっしゃいました。
アマミコとシニレクが矛で揺れ動く島々をかき回したところ、島々がひとつに固まって
立派な台地になりました。そこでその土地の最も高い山(アマンデー)に降り立ちました。
アマンデーは奄美岳ですから、最も高い湯湾岳がアマンデー、奄美岳というわけでしょうか。

標識を左に曲がって少し進むと、眺望の開けた場所があります。
開けたというよりは、無理矢理開いたという感じですけど……(*^.^*)
雨間の夕暮れ時の島影は、なんだか神々しい雰囲気でした。


帰り道に見た、リュウキュウイチゴの花とオーストンオオアカゲラです。
タグ :湯湾岳
2010年02月02日
湯湾岳 前編

1月24日(日)湯湾岳に行ってきました。
途中、小宿の旧堤防を探したり、大和村でウラジロガシを見たりしていたら
すっかり遅くなってしまいました。駆け足で登山道を登ります。


左はマンリョウ、右はユワンツチトリモチ。
まだ少し残っていました。

登り着いたところに、赤い鳥居がありました。
中の広場にいくつかの御堂と石碑があります。


左は「天左諸神神璽」と書いてあります。
右は、手前の石碑が「大島酋長 與湾大親」、奥の御堂は「奄美岳大師御堂」です。


右の石碑には「嗚呼大島開闢始祖 奄麻美古 志爾禮久 二神降臨之霊地 明治37年9月16日」
とあります。
左の2基の内、右には「アマミコノミコト」とカタカナで彫ってあります。
左は文字が彫ってあるのかさえ判然としませんが、おそらく「シニレクノミコト」でしょう。
古事記・日本書紀のイザナギ・イザナミのように男女二神が天から降りてきて国造りをします。
このスタイルが世界共通なのか、
東征をした一族と、奄美を支配した一族は同族だったのか……。
ただ奄美の伝承は「アマミコ神話」と言うようです。
「アマミコ・シニレク」と言いますが「シニレク・アマミコ」とは言いません。
先ほどの二基の石碑もはじめから「シニレク」は書いてなかったのかもしれません。
母系制社会の形を色濃く残しているように思われます。
2010年02月01日
春の息吹

市(いち)集落から嘉徳(かとく)集落に行く林道の傍らで見つけました。
木漏れ日の中で
赤く輝いていましたので
何の花だろうと近づいていったら
木の葉の若芽でした。
何という木かわからないのが残念。
調べる間にタイミングを逃すので
わからないままでアップしました。
ご存じの方、教えてください。
季節感が薄いと言われる奄美ですが、
つぎにやってくる季節の準備が着々と進められています。
ツワ採りの老夫婦も見かけました。

2010年01月30日
西郷蟄居跡

龍郷町の西郷蟄居跡です。
入館料200円でしたが、申し訳ないと思うぐらいに一人のために丁寧に説明をしてくださいました。
愛加那さんの御子孫だそうです。
200円でまかなえるのですかと聞いたら、
正直つらいとのことでした。
一番のネックは「藁葺き屋根の葺き替えだ」とか。
町からも補助をいただいているが、手出しの部分もあるので、
簡単には葺き替えられないそうです。

この家は、最初に建てた家が1909(明治42)年の地震で倒壊したので建て直し、
更に1951(昭和26)年の台風でも倒壊したので、もとの木材を使用し、
一部資材の取り替えを行って原型に復元したものです。
この家に、1891(文久元)年11月20日に
愛加那と息子の菊次郎とともに入居しました。
興南会発行 川畑満州夫著 『西郷隆盛とその妻「愛加那」』という本があって、
奄美に流謫になったいきさつ、愛加那との結婚、別れなど大変詳しく書いてありました。
2001(平成13)年刊の小冊子です。

2010年01月29日
高倉の葺き替え

龍郷町役場を通りかかったところ、高倉が葺き替え作業中のようでした。
写真を撮った日は土砂降りでしたので作業は中断されていたんだろうと思います。
てっぺんからブルーシートで覆われていました。
かなりおおきな8本柱の高倉です。
建物の中に、雨に濡れないようにでしょうか茅をたくさん入れてありました。
今回の葺き替えには1000束以上集めたそうです。
龍郷町秋名集落の人々が中心になって作業に取り組んでいます。

何に使うのでしょうか。茅の中にあちこち差し込んで、動かないようにするのでしょうか。
秋名集落では、集落の中にも、また、田袋の奥にも高倉を見ることができます。
西郷住居の管理をしている方も葺き替えは秋名の皆さんにお願いするといっていました。
徒然草の大井の土民が水車を結う話を思い出します。
費用が約150万円ということになっていますが、その経費はもちろん、
高倉を葺き替える技術の継承が一つの課題となっているようです。
教育委員会の方にお伺いしたところ、
平成7年調査で、わらぶき屋根から改造されたものも含めて
龍郷町内の高倉の数は51棟あったそうです。
現在は30棟ぐらいでしょうかとのことでした。
こちらは、秋名の田袋の奥にある高倉です。

2010年01月28日
大棚(おおだな)

大和村立大棚小中学校です。
奄美市中心部から25kmぐらいです。

大棚商店です。
大棚小中学校の前にあります。
飲み物とビスケットを買い込みました。
にぎわっていて、レジで待ちました。
こういっては失礼ですが、意外でした。
これから、湯湾岳に登ろうと思っています。
2010年01月27日
奄美野生生物保護センター

大和村役場前から見た、大和村公民館です。
独特の形ですね。
何かをイメージしているようです。
すぐ右手、川向かいに群倉(ぼれぐら)がありますので
色といい、高倉をイメージしているのでしょうね。
公民館の中には、図書室もあります。
小さな図書室ですが、村民のためにがんばっています。

移動図書館車が本の積み替えをしていました。
学校などを回ったりして、本を待っている人の所に届けてくれます。
このような車をBMといいます。ブックモバイル(bookmobile)の略です。
奄美のような集落が浦々に点在していたり、山に遮られていたりするようなところでは重宝します。
ちなみに、東京都のような交通網が発達したところでは必要性が薄く、
23区全てで2005年までにBMシステムは廃止されました。
公民館の奥に、奄美野生生物保護センターがあります。

奄美野生生物保護センターでは、
アマミノクロウサギ、オオトラツグミ、アマミヤマシギなどの希少な野生生物や
奄美固有の生き物を中心に、野生生物の保護や、
自然への理解を深めてもらうための展示、資料作りなどをしています。
奄美の野生保護の中心的施設ではないかと思います。
■ 開館時間: 午前10時~午後4時30分
■ 休館日 : 毎週月曜日、みどりの日およびこどもの日をのぞく祝日及び年末年始
■ 住 所 : 鹿児島県大島郡大和村思勝字腰ノ畑551番地
■ 電 話 : 0997-55-8620
■ 管理協力: 鹿児島県環境保護課、大和村等
■ メールアドレス: RO-AMAMI@env.go.jp
2010年01月27日
奄美野生生物保護センター

大和村役場前から見た、大和村公民館です。
独特の形ですね。
何かをイメージしているようです。
すぐ右手、川向かいに群倉(ぼれぐら)がありますので
色といい、高倉をイメージしているのでしょうね。
公民館の中には、図書室もあります。
小さな図書室ですが、村民のためにがんばっています。

移動図書館車が本の積み替えをしていました。
学校などを回ったりして、本を待っている人の所に届けてくれます。
このような車をBMといいます。ブックモバイル(bookmobile)の略です。
奄美のような集落が浦々に点在していたり、山に遮られていたりするようなところでは重宝します。
ちなみに、東京都のような交通網が発達したところでは必要性が薄く、
23区全てで2005年までにBMシステムは廃止されました。
公民館の奥に、奄美野生生物保護センターがあります。

奄美野生生物保護センターでは、
アマミノクロウサギ、オオトラツグミ、アマミヤマシギなどの希少な野生生物や
奄美固有の生き物を中心に、野生生物の保護や、
自然への理解を深めてもらうための展示、資料作りなどをしています。
奄美の野生保護の中心的施設ではないかと思います。
■ 開館時間: 午前10時~午後4時30分
■ 休館日 : 毎週月曜日、みどりの日およびこどもの日をのぞく祝日及び年末年始
■ 住 所 : 鹿児島県大島郡大和村思勝字腰ノ畑551番地
■ 電 話 : 0997-55-8620
■ 管理協力: 鹿児島県環境保護課、大和村等
■ メールアドレス: RO-AMAMI@env.go.jp
2010年01月27日
奄美野生生物保護センター

大和村役場前から見た、大和村公民館です。
独特の形ですね。
何かをイメージしているようです。
すぐ右手、川向かいに群倉(ぼれぐら)がありますので
色といい、高倉をイメージしているのでしょうね。
公民館の中には、図書室もあります。
小さな図書室ですが、村民のためにがんばっています。

移動図書館車が本の積み替えをしていました。
学校などを回ったりして、本を待っている人の所に届けてくれます。
このような車をBMといいます。ブックモバイル(bookmobile)の略です。
奄美のような集落が浦々に点在していたり、山に遮られていたりするようなところでは重宝します。
ちなみに、東京都のような交通網が発達したところでは必要性が薄く、
23区全てで2005年までにBMシステムは廃止されました。
公民館の奥に、奄美野生生物保護センターがあります。

奄美野生生物保護センターでは、
アマミノクロウサギ、オオトラツグミ、アマミヤマシギなどの希少な野生生物や
奄美固有の生き物を中心に、野生生物の保護や、
自然への理解を深めてもらうための展示、資料作りなどをしています。
奄美の野生保護の中心的施設ではないかと思います。
■ 開館時間: 午前10時~午後4時30分
■ 休館日 : 毎週月曜日、みどりの日およびこどもの日をのぞく祝日及び年末年始
■ 住 所 : 鹿児島県大島郡大和村思勝字腰ノ畑551番地
■ 電 話 : 0997-55-8620
■ 管理協力: 鹿児島県環境保護課、大和村等
■ メールアドレス: RO-AMAMI@env.go.jp
2010年01月26日
オキナワウラジロガシ林


大和村にやってきました。
大和村役場の右裏手の森が「大和浜オキナワウラジロガシ林」です。
集落民有地で国指定・天然記念物になっています。
衛星通信の大きなアンテナがありました。この右を通って裏山に行きます。


登り口の所に、渓流が流れています。
岩場の左側に小さな石の塔があって、神の祭りが行われていたそうです。
写ってはいるのですが、ちょっとわかりませんね、すみません。
このあたりは、祭りが行われていたころは10人ぐらいは座れるほどのちょっとした祭壇だったようですが
今は木が次々に生えてきて、教えてもらえば地形にその跡をようやく認められる程度になっています。


サクラツツジが登り道のあちこちに美しく咲いています。
ようやく目的地に着きました。
大きなウラジロガシを一周するように、木造の回廊で囲まれていました。

登り口の所に立っていた案内板を引用します。
北限域の奄美大島で、集落の神山として良好にのこされた代表的な森林である。
戦後の混乱期においても、周囲の森林の伐採が進む中にあって
当該地は聖域として大切に守られ伐採を免れてきた。
琉球列島の固有種で代表的森林を形成し、北限域の奄美大島で
数少ないオキナワウラジロガシの自然林として学術的価値が高く貴重である。
文章から、この森を守ってきた村民の自負とプライドとが読みとれます。
登山道が整備されています。
ハイヒールではきついかもしれません。
タグ :オキナワウラジロガシ大和村
2010年01月25日
小宿(こしゅく)埋立俯瞰図

昨日のブログを見たHさんが、小宿町の全体が見える写真を提供してくださいました。
2010年1月1日に小宿町厳島神社から撮影したものだそうです。
厳島神社は、平成19年7月に改築されて、小宿小の後ろの山に美しい社殿を見せています。

手前の、黄色い帯が掛かっている部分が本来の小宿の集落です。
この地区には、古くからの建物も残っています。
漁村だったようです。
1984(昭和54)年3月に、全工区が完成しました。
322,077㎡、サッカーグランド40面分です。
サッカーグランド40面分という表現は、広いんだか狭いんだかよくわかりませんね……(*^.^*)
応援スタンドを含めた甲子園球場全体の8個半というのはどうでしょうか。
さて、小宿の埋立地はいつ出来たのだろうと思って調べましたが、
ネット検索ではなかなかヒットしませんでした。
それが、ひょんなことから
「奄美土木史年表」という本にいきあたり、1984(昭和54)年3月という日を知ることができました。

入佐一俊著 平成4年9月刊行です。
入佐さんは、前書きや後書きから推測しますに、県職員でいらしたようです。
「年末年始の休暇中にでもできあがる」ぐらいのつもりで作りはじめたそうですが
古くなるほど記録は残っていないものもあり、2年半以上かけて完成されたようです。
正確な記録、しかも系統的に保存してある記録は大切です。
平成4年以降の記録はどうなっているのでしょうか。
2010年01月24日
小宿(こしゅく)町

県道79号線を大和村に向けて走っています。
小宿トンネルの手前から、海岸線を回って小宿町にはいることにしました。

埋め立てられて海岸線がなくなっています。
今では立派な住宅街ができあがっています。
元々の海岸線を探しに行ってみましょう。
小宿郵便局の前を、小宿小学校方面に左折します。


かつての堤防がそのままの形で残っていました。
ロープが残っていますが、船をつないでいた当時のものでは、まさかちがいますよね。

右が埋め立てられたところ。
左には山がすぐ後ろまで迫っています。
小宿はかなり小さな集落だったことが分かります。
海岸線を回る道路もなかったのかもしれません。
古地図がほしいですね。
新興住宅街として、一時は人口もかなり増えましたが、
2009年12月の推計人口は706人、351戸です。
戸数と人口を比較してみると、住宅地自体が年老いていることが分かります。
育った若者が出て行く一方なのでしょうね。
海岸沿いに立ち並ぶアパートの入居者探しが難しくなるかもしれません。
タグ :小宿町